本記事にはプロモーションが含まれます。
この記事ではカメラ初心者がカメラやマクロ撮影について書いております。
あくまでも個人の意見であり、検証は完璧に正確なものでは無いことをご了承ください。
また、カメラ上級者の方がお読みになると時間の無駄になってしまうと思われます。
使って分かった接写リングのデメリット!
①カメラとレンズの二箇所つけ外しが地味に面倒臭い。
これはカメラとレンズを一つずつしか持っていない私には地味に面倒臭いところです。
また、つけ外しを億劫に感じてしまうのは電子接点の繋がりづらさもあるんです。
②電子接点が合わず繋がらないことが多い。
一旦電源オフにしてちょっとだけずらしてまたカチャンとはめ直すと直るのですが、ちょっと面倒です・・・。
③フレアが出ることがある。

この写真では52mm延長しています。
30mm以上接写リングを重ね付けすると、たまに中心にこういったフレアが出ることがありピントが合わせづらくなります。
そんなにいつも出る訳では無く、どういった条件で出てしまうのかまだはっきり分かっていないのですが、一度出てしまうと画面に付き纏いまるで白内障のような歯痒さです。
上記の写真の時は、純正のレンズフードを着用してみたりしましたが意味は無かったです。
この写真の時は屋外での撮影で逆光だったので、レンズ内に光が入るとこのようになるのかもしれません。
屋内で飼育ケース内の生物を撮影していてもライトが飼育ケースに反射するとこのように円形のフレアが出ます。
何故接写リングを重ねるとフレアが出るのでしょうか。
答えは私が買った接写リングのレビューにありました。
何で接写リングでフレアが出るの?
残念ながら、この製品には大きな欠点があります。
内装はなめらかです。素材 (プラスチック) は光を反射するため、画像には常に望ましくない光の反射が生じます。
より優れた (必ずしも高価で製造が良いというわけでもない) エクステンションリングは、光が反射されずに取り込まれるように、センサーと平行に内側に多くの溝があります。レポートAmazonによってドイツ語から翻訳されました
引用元:Amazon.co.jp
https://www.amazon.co.jp/Meike-mk-p-af3a-Panasonic-Olympus-/product-reviews/B06XTMWMVJ
有用なレビューをありがとうございます、ドイツの人。

溝付きはフレア対策になる?
接写リングやマウントアダプター等は鏡筒内に乱反射防止対策の溝が入った物を選ぶのが良いようです。
ですが、少なくともマイクロフォーサーズで溝の入った接写リングを作っているのは「Viltrox」という中国企業一つしか見つけられませんでした。
こちらの商品はあんまりレビューの評価が良くなく「ガタつく」と言われているのでこれはこれでまた別の悩みが出てきそうです。
少しの揺れでピントがずれてしまうマクロ撮影でガタつきは致命的ですね。
低反射塗料はフレア対策になる?
99%以上の光を吸収する「超低反射塗料」という真っ黒の塗料があるようで「鏡筒内にこれを塗ればいいのか!」と閃いたりもしましたが、この塗料は粉をくっつけたようにザラザラしていて触るとすぐに剥がれてしまうようです。
C-PLフィルターはフレア対策になる?
C-PLフィルターという反射を抑えるためのフィルターはフレアの軽減になるでしょうか?
検証してみました。

上段左の写真では強い光で本来の色が失われていますが、C-PLフィルターによって本来の色みにちかくなっています。
ただ、ますますピントが合わせづらくなったのと少し画質が低下しています。
下段はスマホの画面を写したものですが、反射を抑えているというよりただ全体が暗くなっているだけのように感じます。
あんまり良さは感じなかったです。
④トリミングすれば同じ?!
接写リングの使用で画質は劣化しないとされていますが、本当でしょうか?
検証してみました。
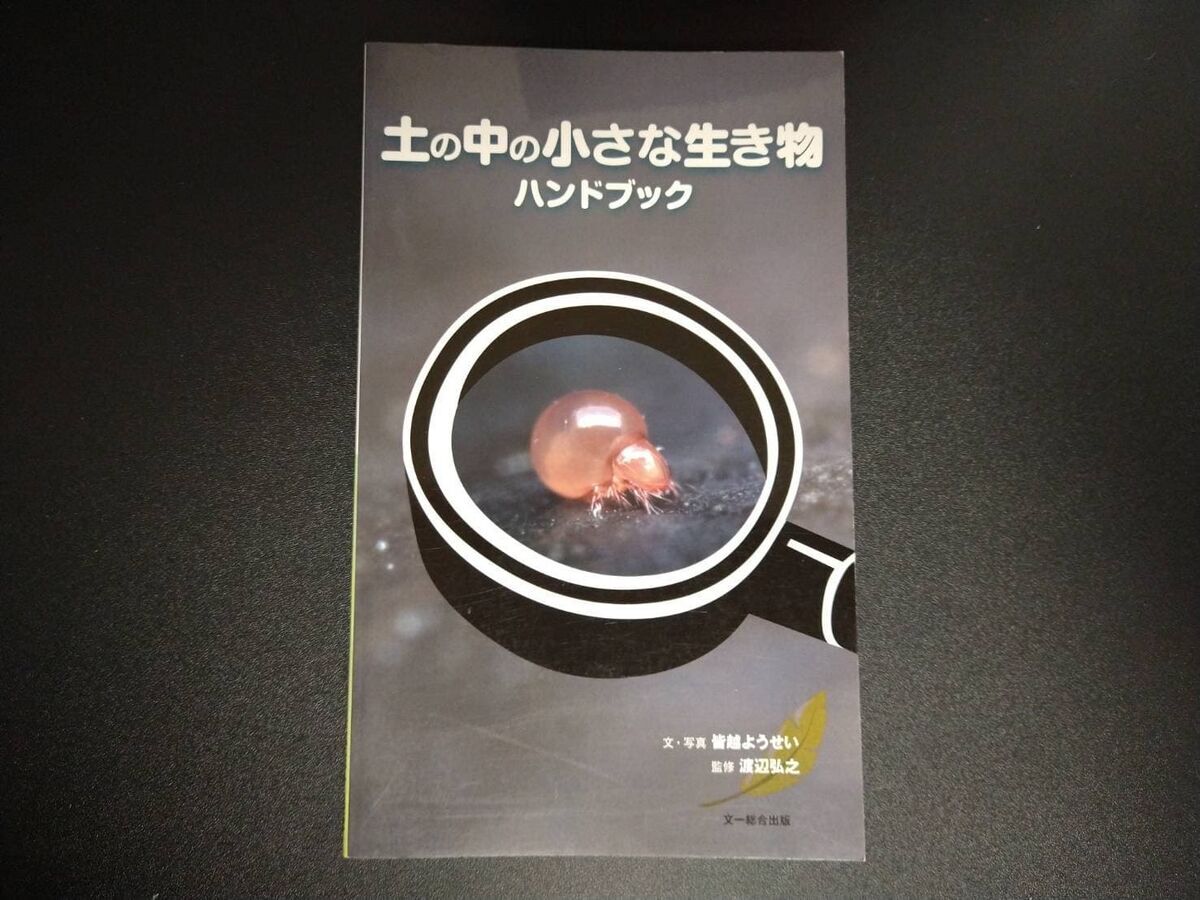
使用する機材は前編と同じく以下の通りです。
カメラ:OM SYSTEM OM-5(マイクロフォーサーズ)
レンズ:M.ZUIKO DIGITAL ED 60mm F2.8 Macro(等倍マクロ)
接写リング:Meike mk-p-af3a
まずは、普通に接写リング不使用で撮影した写真と52mm延長して撮影した画像の比較です。
二つの写真で光源の強さや位置は変えていません。
52mm延長した下の画像では約2.5倍マクロとなっています。

次は上の接写リング不使用の写真を接写リングで52mm延長した写真と同じくらいに拡大して並べてみました。

接写リングを使用すると画面が暗くなりますが、暗いせいで52mm延長の方が画質が悪くなってますね・・・。
じゃあ、画質が悪くならないように明るく撮影して再チャレンジ。

この比較を見ると、きちんと明るく撮影すれば延長リング使用の方がくっきり撮影できることが分かります。
ですが、明るく撮影するために強い光を当てたせいで色褪せたように白っぽくなっています。(これもフレア?)
光の当たる部分は青みがかり、影は赤みを感じます。
次は光の当てすぎに注意してまた再チャレンジします。
ついでに、今度は手持ちの撮影機材を全て比較してみます。
塩の一粒を極限まで大きく高画質で撮影しました。

マイクロスコープの画像のみトリミングをしていません。
それ以外の写真はマイクロスコープで撮れた写真に合わせて同じくらいの大きさにまで拡大トリミングしています。
上から3番目は接写リング無しで等倍マクロレンズを使用して撮影した写真です。
ここまでトリミングすると、背景がとてもザラザラしていますね。
上から4番目は接写リングを52mm付けて約2.5倍マクロにして撮影した写真です。
この中では一番綺麗に仕上がっているように見えます。
ここまでやってようやく、接写リングの効果を発揮させることができました。
どれもくっきりと撮れていますが、マイクロスコープは近距離で上から光を当てるため塩の立体感が消えています。
コンデジ(tg-6)も最短撮影距離が短く真上から撮っているため立体感がありません。
一方、マクロレンズ(zuiko60mm)の方はレンズの先端から9cmも距離を取れるため立体感のある角度で撮影できています。
物の姿を記録するためには、倍率や画素数よりも距離を取れることが大事だと分かりました。
結論
・接写リングを使うなら光の角度と強さに気をつけて使う
・接写リングを使ったせいで画面が暗くなってしまうくらいなら、接写リングを使わずに光をしっかり当てしっかりピントを合わせて撮ったものをトリミングした方が綺麗な画像が得られる。三脚とビデオライト必須。
・最短撮影距離の長さ・光・構図 > 倍率・画素数
・接写リングを買ってもすぐに本当のマクロレンズが欲しくなる
最後に、接写リングを使って撮影した動画を載せておきます。
接写リングでこんなのを撮ってます
とても作例とは呼べないクオリティーですが、アカイボトビムシが可愛いのでご覧ください。
この虫の体長は1〜2mm程度です。
52mmで撮影してトリミングしました。
中心にフレアが出て明るくなっていますよね。
また、手持ちなので後から手ぶれ補正加工してもブレッッブレです。
ここまでお読みいただきありがとうございました。
ご参考になれば幸いです。
\ 気になるマクロレンズ、試せます。 /
【関連記事】

